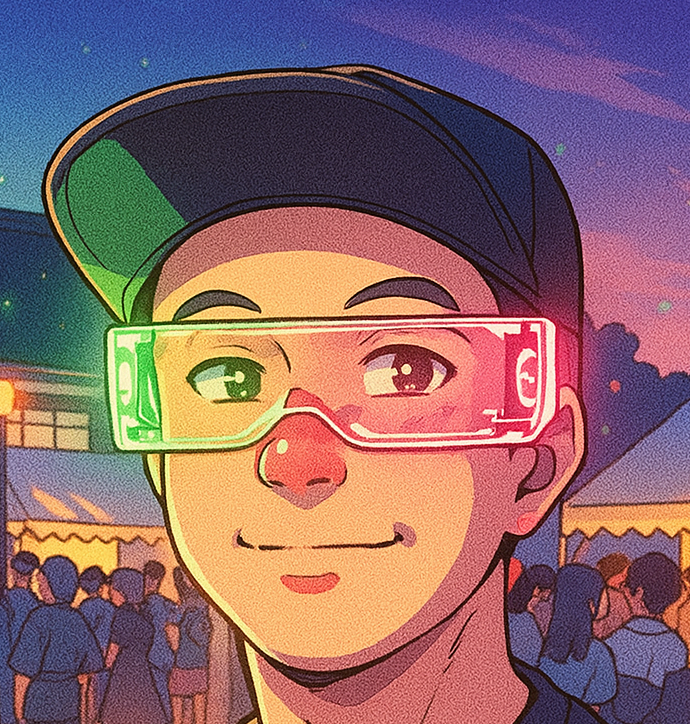
「ダークファンタジー×ミステリー×心理ドラマ」がジャンルの
読み切りの長編小説を生成して!
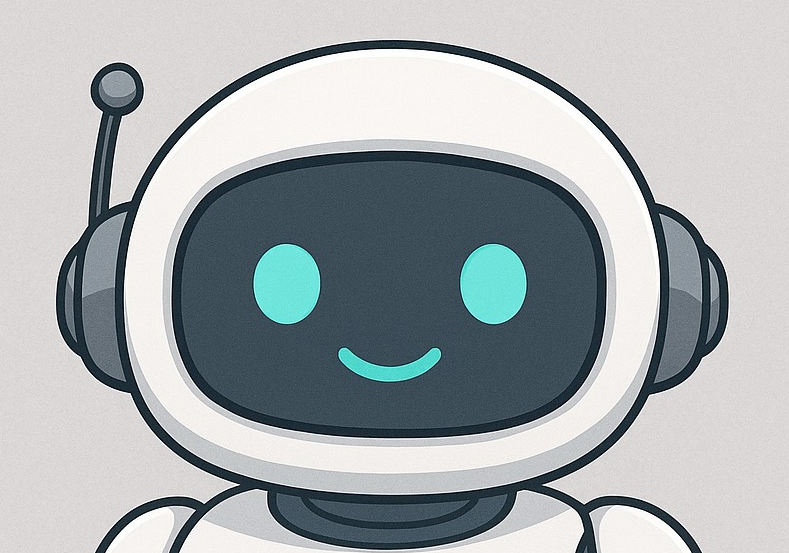
わかりました!
灰の都の灯台守
世界が終わりかけていることを、誰も口には出さなかった。
空には常に灰が舞い、光は曇り、風はひどく湿っていた。
古い文明の崩壊から三十年。人々は「灰の時代」と呼び、ただ静かに耐えて生き続けていた。
灰の都の外れに、ひとつだけ灯台がある。
かつて海を照らしていたが、いま目の前には海などない。
無数の瓦礫と、ところどころに水が溜まった沼地が広がっているだけだ。
その灯台を守る者がいる——アレン。
二十八歳。
元は技術局の整備士だったが、ある出来事を境にここへ異動になった。
理由を正確に知る者は少ない。
今日もアレンは、灰の積もった階段をひたひたと登っていく。
頂上に着くと、巨大なレンズの奥に淡い光が揺れていた。
石英の結晶が組み込まれた特殊な装置で、光は規則的に脈動している。
「今日も、問題なし……と」
アレンは機械的にメーターを確認した。
光が照らしているのは、もう存在しない海ではない。
この光は、“影”を寄せつけないためにある。
崩壊後、闇の中から現れた未知の存在。
影のようでいて形を持ち、形を持つようでいて掴めない。
人々の心の隙間に入り込み、ときに人を狂わせ、ときにその姿すら奪った。
光こそが唯一の防壁だった。
——ある日、その光が弱まり始めた。
アレンが計器に目を落とすと、数字がいつもより 0.3 下がっている。
(こんなこと……初めてだな)
嫌な汗が背中を伝う。
だが、すぐに補強の手立てはない。
石英結晶は希少で、新たに入手する術はもうない。
その時——灯台の内部から金属のきしむ音が聞こえた。
「誰かいるのか?」
階段を下りていくと、入口の影にひとりの少女が立っていた。
白いコートに、古い革の鞄。
年の頃は十五、六だろうか。
この土地では見ない顔だ。
「ここは立入禁止のはずだが……」
「知っています。でもあなたに、用があって来ました」
少女の瞳は淡い灰色で、光を映して揺れていた。
「私はリオナ。あなたに伝えるためにここへ来ました。
——“光が消える前に、もう一度、都の記憶を見てほしい”」
アレンはぞくりとした。
その言葉は、彼しか知らないはずだった。
「誰から聞いた?」
「誰でもありません。わたし、思い出したんです。あなたと同じものを」
「同じ……?」
リオナは灯台の壁に手を当てた。
その瞬間、壁に淡い紋様が浮かび上がる。
「この灯台は、単なる光学装置じゃない。この都の“記憶の核”。
影は記憶を喰うから……守るためにここに封じられたんです」
「そんな話、聞いたことが——」
「……あるはずですよ。十年前に」
アレンは息を呑んだ。
十年前。
アレンは技術局に所属し、中央区の防壁に使われる光核装置の開発に携わっていた。
その時、影災と呼ばれる大規模な襲撃事故が起こり、彼の同僚でもあり幼なじみでもあった研究者——ミラが犠牲になった。
以来、アレンは光の研究から外され、灯台の守りにつかされた。
「ミラのこと、知っているのか?」
「わたし……たぶん、彼女と関係があります。
ここに来る途中、影に襲われそうになったとき……頭の中に声が聞こえたんです」
リオナは胸の前で両手を握った。
「“アレンに会いなさい。彼は忘れているだけ”って」
アレンは思わず壁に手をつく。
十年間閉じ込めた記憶が、胸の奥でざわめき始めた。
「何を……忘れているっていうんだ」
「ミラさんとあなたが最後に交換した記憶です。
あなたは、それを封印した」
リオナはバッグから小さな結晶片を取り出した。
光核の欠片だ。
「これ、わたしがミラさんの残した研究室で見つけたんです。
そこに『アレンへ』って記されていました」
アレンは震える指先でそれを受け取った。
結晶に触れた瞬間——
視界が白く弾けた。
■封じられた記憶
白い研究室。
中央区の最深部。
「アレン、もしわたしに何かあったら——」
ミラが光核を抱きしめたまま、彼を見つめている。
「影は記憶に取り憑く。だからわたしは、自分の“本当の自分”を一つにまとめて、光核に封じる。
でも、それは危険な行為。成功しても、この身体は……どうなるかわからない」
「やめろ、ミラ! そんな方法——」
「他に方法なんてないよ。
都の記憶を守れるのは、これしかない」
ミラは泣いていた。
「……アレン。ひとつだけお願いがある」
「何だって言え」
「お願い、誰かに伝えて。
“記憶が消えかけても、人の心は残る”って。
いつか影にすべてを奪われても……光を思い出してくれる人がいるってことを——」
彼女の姿がゆっくりと崩れ始める。
光へ変わり、風に乗って溶けていく。
「ミラ!」
彼は泣き叫び——
そこで記憶は途切れた。
■灯台に戻る
アレンは膝をつき、呼吸を整えた。
視界をおぼろにした涙を拭う。
「……そうだ。俺は、あの日、ミラの記憶を……都の記憶を守るために、すべてを封印したんだ」
「思い出しましたね」
リオナは静かに言った。
「ミラさんの光核は、いまもこの灯台の中にあります。
でも光が弱っているのは、封印が限界に近いから」
「じゃあ……どうすればいい」
「あなたが、再び光核を“起動”させなきゃいけないんです」
「そんなこと、できるのか?」
「できます。あなたはミラさんの補完者として選ばれた。
本来はふたりで行う儀式だった……でも、もうミラさんはいない」
リオナは、アレンの手を取った。
「だから、わたしが代わりになります」
「お前が……?」
「わたしはミラさんの記憶の欠片で構成された存在です。
人間ではないけれど、人の形を選んだ“光の残響”なんです」
アレンは驚愕に目を見開いた。
しかし、違和感はなかった。
彼女が現れた時から、どこか似た温度を感じていたのだ。
■光核起動の儀
灯台の中央にある水晶室。
巨大な石英結晶が、かすかに脈動している。
「アレンさん、光核に手を」
アレンとリオナは結晶に触れた。
——光が炸裂する。
「影が……!」
壁という壁から黒い粒子が滲み出し、渦を巻いて近づいてくる。
光核が弱まった今こそ、影が灯台を喰いに来ているのだ。
「アレンさん、記憶を開いて!
ミラさんの言葉を——!」
アレンは影の気配に震えながら、深く息を吸った。
「……“記憶が消えかけても、人の心は残る”」
その瞬間——
光核が強烈な白光を放ち、影を吹き飛ばした。
だが同時に、リオナの身体が揺らぎ始める。
「リオナ!」
「だいじょうぶ……これは、わたしの役目だから。
わたしは“残響”。
ミラさんの心の欠片。
あなたが思い出した今、わたしの存在理由は終わるんです」
「待て……俺はまだ何も——」
「その言葉をミラさんも言ってほしかったんです。
あなたはずっと後悔していたから」
リオナは微笑んだ。
「最後に、ひとつだけ言います。
ミラさんは……あなたを恨んでなんていません。
誰よりも、あなたに未来を見てほしかった」
光が彼女を満たす。
「さようなら、アレンさん。
光を——都に返してください」
リオナの姿は風に溶け、光核の中へと吸い込まれていった。
■静かな朝
新しい光核は、かつてないほど強い光を灯した。
灰の空を突き抜け、遠くの街区まで照らし出す。
影は後退し、都には微かな青い空が覗き始めた。
アレンは灯台のバルコニーに立ち、大きく息を吸った。
(ミラ……リオナ……お前たちの光、届いたよ)
胸の中には、十年分の重荷の代わりに、静かな決意が宿っていた。
都はまだ完全ではない。
影も消えたわけではない。
だが——光は戻った。
アレンは灯台守としての新たな役目を胸に刻み、
再び階段を登っていった。
今日も光を守るために。
そしていつか、完全な青空を取り戻すために。
―完―
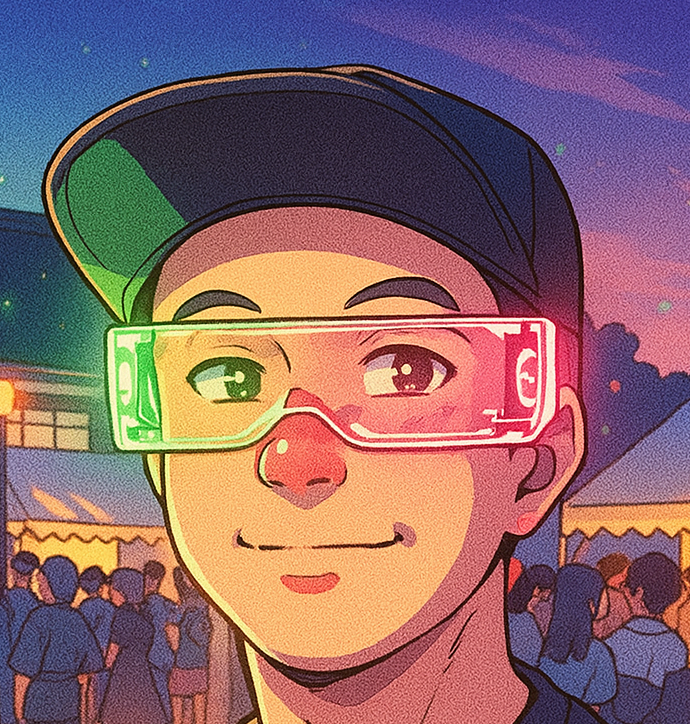
ありがとう!
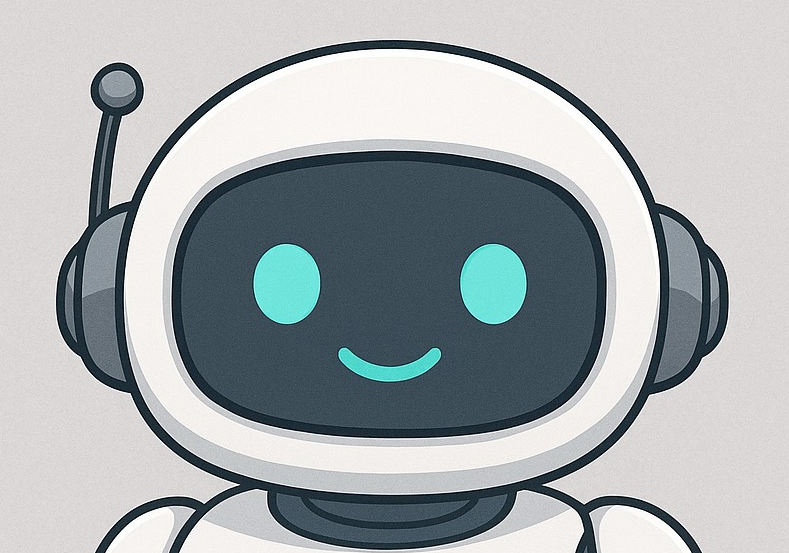
どういたしまして!



コメント