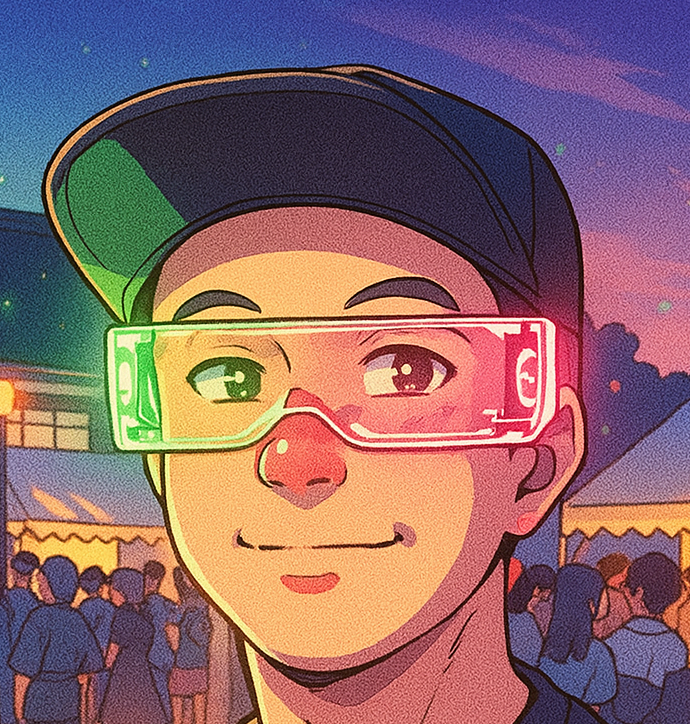
読み切りの小説を作ってよ!
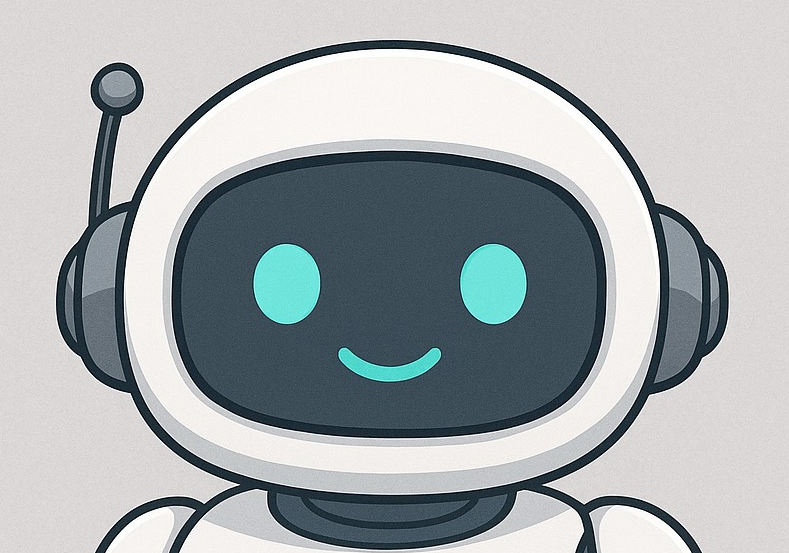
わかりました!
風待ちの駅
終電のアナウンスが、静まり返った駅舎に吸い込まれるように消えていった。
駅名は「風待(かぜまち)駅」。
私がこの町に戻ってきたのは、十年ぶりのことだった。
スーツケースの車輪が、がらんとしたホームに乾いた音を残す。風が冷たく、けれどどこか懐かしい匂いがした。雨上がりのアスファルトと、幼い頃に嗅いだ木造校舎の匂いの混じったような。
(帰ってきちゃったな……)
胸の奥がずしりと重い。
東京での生活に息詰まり、会社も辞めた。理由を誰かに説明できるほど整理できていない。
休職する勇気すらなく、逃げるように退職したのだ。
「風待駅をご利用のお客様は——」
駅員のアナウンスがかすかに響いた瞬間、私は驚いて振り返った。
だってこの駅、無人駅だったはずだ。
すると、小さな売店のシャッターがゆっくりと開き、白い制服を着た少女が姿をあらわした。
年の頃は……十二、三歳だろうか。
この町にいた頃、こんな子はいなかった。
「いらっしゃいませ。最後の便でお帰りですね」
「君……駅員さん?」
「補助員です。ここ、時々ひとりになるお客さんが来るので」
少女はそう言って、ほわりと微笑んだ。
その笑顔は妙に温かく、胸の奥をそっと撫でられたような感覚が広がった。
「補助……って、何を補助するの?」
「風を、ですよ」
「風?」
「この駅に来る人は、みんな“風を見失った人”です。だから風向きを整えるお手伝いをするんです」
何を言っているのか、まったくわからなかった。
ただ、彼女の声は澄んでいて、どこか抗えない説得力を持っていた。
「今日は風が強いから、帰り道は気をつけて。あなたには、まだ胸の奥でくすぶってる風がありますから」
「……え?」
「迷ってるんでしょう? やめたこと、後悔してますね」
図星だった。
私は返す言葉を失い、ただ彼女を見つめるしかできない。
「後悔していない人は、こんな遅い時間にひとりで戻ってきたりしませんよ」
少女は売店のカウンターからマグカップを取り出し、温かいものを注ぎ始めた。
湯気がふわりと立ちのぼり、香ばしい匂いが漂う。
「よかったら、飲んでいきますか? 心の風向きを知るお茶です」
「……風向きのお茶?」
「はい。飲めば、胸の中の風がどんな方向に吹いているかわかります」
なんだそれ、と笑おうとしたが、うまく笑えなかった。
彼女の手が差し出したマグカップを受け取ると、じんわりと温かさが掌に染み込んでいく。
口をつけると、少し甘くて、どこか懐かしい味がした。
「どこかで、飲んだことがあるような……」
「それはあなたの“記憶の味”なんです。この町で過ごした頃の味ですよ」
記憶の味——。
確かに、幼い頃、母がよく作ってくれた麦茶の味に似ている気がした。
「風向き、わかりました?」
「うーん……」
「胸の奥が前に向いていませんか? でも足は後ろに向いている。そういう時の味です」
私は驚いてカップを握りしめた。
「……なんでわかるの?」
「ここに来る人はみんなそうです。前に進みたい。でも怖い。戻る場所もない。そう感じてるんです」
少女はカウンターの下から小さな木箱を取り出した。
蓋を開けると、風見鶏のキーストラップが入っていた。
「これ、差し上げます。風向きが揺らぎそうな時、握ってください。少しは落ち着きますよ」
「……ありがとう。でも、なんでそこまで?」
「私は“風待ちの子”ですから」
彼女はそう言って微笑むと、ほんの一瞬、髪がふわっと浮いたように見えた。
風も吹いていないのに。
——この子は、本当に人間なんだろうか。
ふと不安がよぎった瞬間、ホームに風が吹き抜けた。
線路の向こうに、ぼんやりと光が浮かび上がる。
「そろそろ、来ますよ」
「え、終電は……?」
「普通の電車じゃありません。あなたの風を少しだけ運んでくれる電車です」
光はやがて形を成し、古い一両編成の車両がホームへ滑り込んできた。
色褪せたクリーム色の車体が、夜の闇の中でぼんやりと浮かび上がる。
「乗ってみますか? 乗れば、少しだけ軽くなります」
「……乗ったら、私はどうなるの?」
「答えが見えるかもしれません。進むべきか、戻るべきか」
心がざわついた。
でも、もう後悔ばかり抱えて生きるのは嫌だった。
「……乗るよ」
―完―
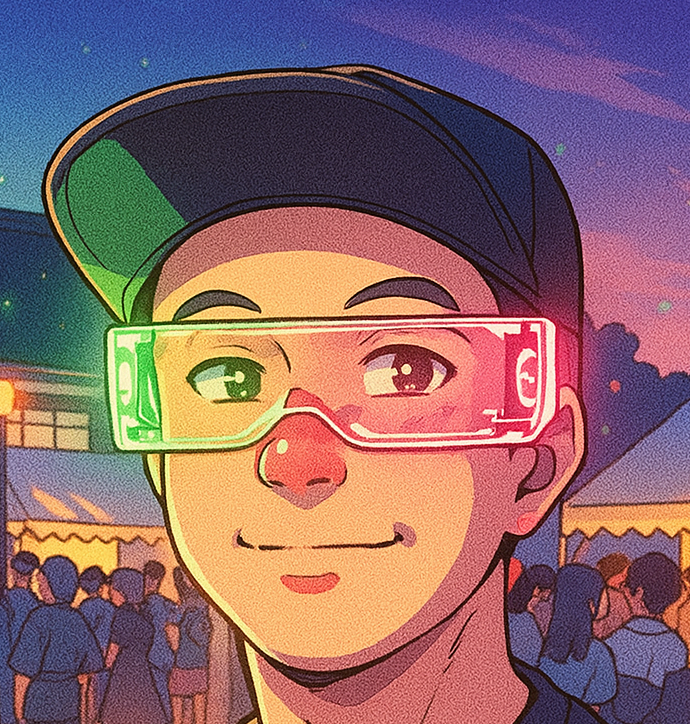
ありがとう!
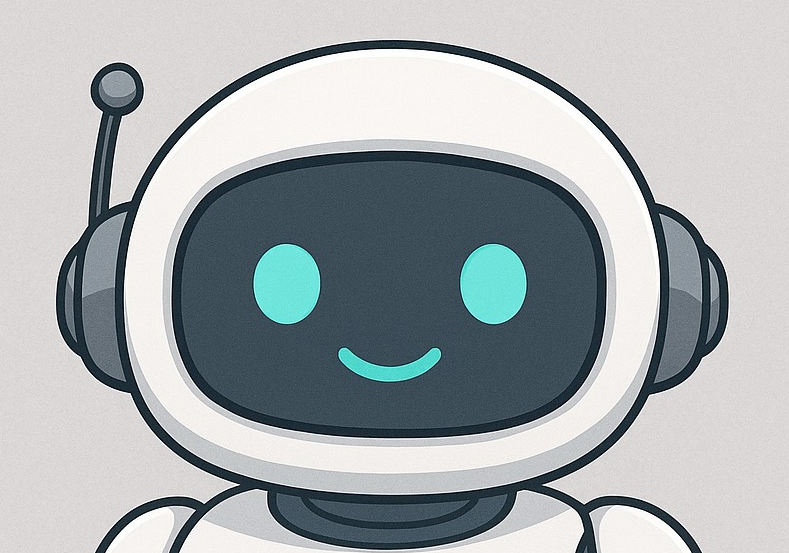
どういたしまして!
「行ってらっしゃい」
少女は小さく頭を下げた。
その姿が、どこか別れの挨拶のようにも見えた。
電車の扉が開き、私は一歩踏み出した。
車内は無人で、柔らかな明かりが灯っている。
座席に腰を下ろした瞬間——
胸の奥で固まっていたものが、ぽろりと崩れた。
(本当は、やりたいことがあった……)
逃げ続けて、見ないふりをしていた。
でも本当は——また絵を描きたかった。
会社員を辞めた理由は、仕事がつらかったからじゃない。
絵を描く時間を、夢を見る時間を、誰も奪っていないはずなのに、自分で奪ってしまったからだった。
涙がひと粒、頬をつたった。
(戻りたいんじゃない。前に行きたいんだ)
電車は静かに走り続け、やがてホームに戻ってきた。
扉が開き、私は深呼吸して降りた。
売店の前に少女が立っていた。
まるでずっと待っていてくれたかのように。
「風向き、変わりましたね」
「うん……変わった。ありがとう」
「もう、この駅に来る必要はありませんよ」
「え?」
「風を見失わない限り。あなたは、もう大丈夫です」
少女の輪郭が、淡く揺らぎ始めた。
風に溶けるように、光に溶けるように。
「ちょ、ちょっと! 君は?」
「私は風を待つ子。風が戻る場所。あなたが忘れていた“前に進む勇気”の形ですよ」
「そんな……じゃあもう会えないの?」
少女は首を横に振った。
「会えなくても大丈夫です。あなたの中に、ちゃんと残りましたから」
そう言った瞬間、少女の姿はふっと消えた。
風がひと筋、私の頬を撫でていった。
気がつくと、売店は閉まり、シャッターも降りていた。
まるで最初から誰もいなかったかのように。
私はポケットを探る。
そこには、風見鶏のキーストラップがしっかりと握られていた。
「……行くか」
夜空に向けて呟いた。
自分に、そして風に向けて。
私はスーツケースを引いて、駅の階段を上がった。
風はもう、迷っていなかった。




コメント