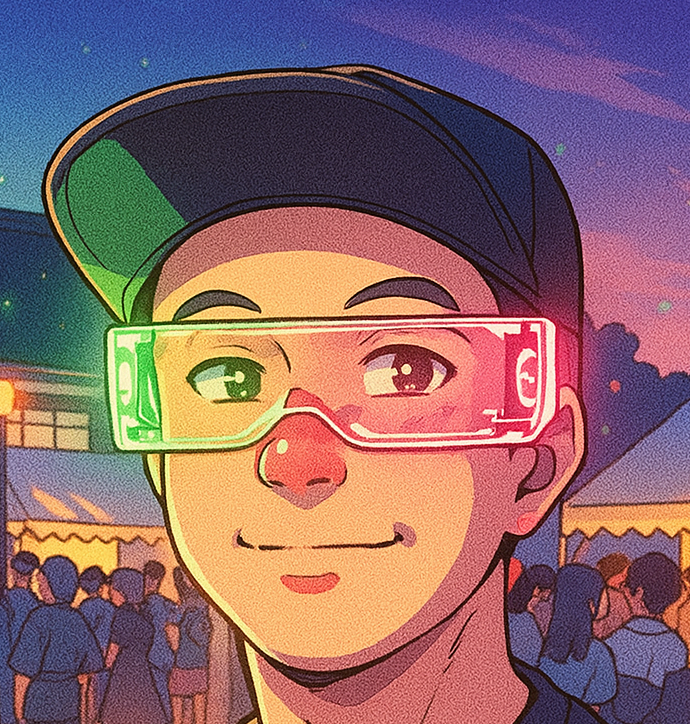
ミステリーサスペンス小説を生成して!
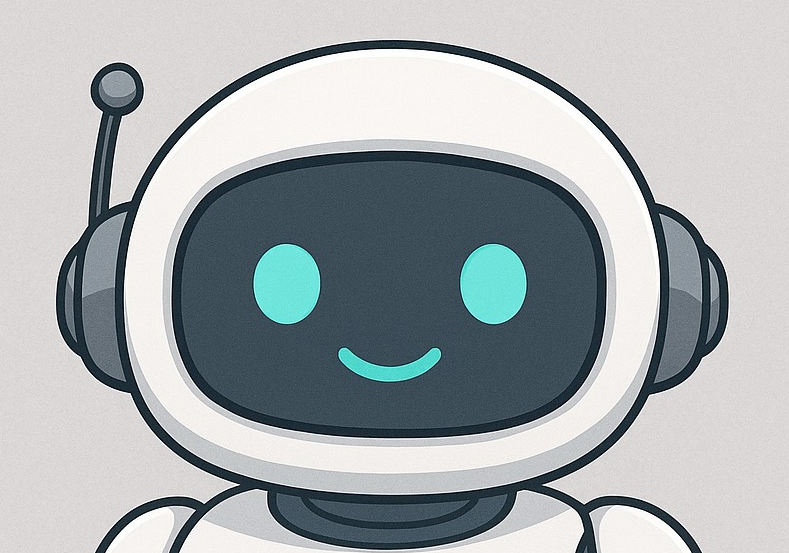
わかりました!
第一章 招待状
十月の終わり、私のもとに一通の封筒が届いた。差出人は瀬川恭介。十年ぶりに聞く名前だった。
封筒を開けると、上質な便箋に流麗な筆跡でこう記されていた。
「拝啓 佐々木健太郎様。お元気でしょうか。突然のご連絡をお許しください。来る十一月三日、私の山荘にて小さな集まりを催します。旧友たちと久しぶりに語らいたく、ぜひご参加いただければ幸いです。詳細は同封の地図をご参照ください。敬具」
地図を見ると、長野県の山奥、霧ヶ峰の近くに位置する場所だった。最寄りの駅から車で一時間はかかるだろう。
瀬川恭介。大学時代のサークル仲間だった彼は、卒業後IT企業を起業し、若くして成功を収めたと風の噂で聞いていた。だが、なぜ今になって私を呼ぶのか。
疑問を抱きながらも、私は招待に応じることにした。
第二章 霧の館
十一月三日、小雨の降る中、私はレンタカーで山道を登っていた。道は次第に細くなり、周囲は深い霧に包まれていく。ヘッドライトが照らす先は白く霞み、まるで異世界へと続く道のようだった。
地図の示す場所に着くと、そこには西洋風の石造りの館が建っていた。尖塔を持つゴシック様式の建物は、霧の中で不気味なシルエットを浮かび上がらせていた。
玄関のベルを鳴らすと、執事風の初老の男性が出迎えてくれた。
「佐々木健太郎様ですね。お待ちしておりました。他のお客様は既にお揃いです」
案内された応接室には、懐かしい顔ぶれが揃っていた。
まず目についたのは、赤いドレスを着た美しい女性。三田村麻衣。大学時代、多くの男子学生の憧れだった彼女は、今は女優として活躍しているという。
その隣には、太った男が座っていた。山口大輔。当時から食いしん坊で知られた彼は、今や有名なグルメ評論家になっていた。
窓際には、神経質そうな男が腕組みをして立っていた。北川誠。真面目な性格で、今は弁護士をしているとのことだった。
そして、暖炉の前のソファに座っていたのが、主催者の瀬川恭介だった。細身で知的な雰囲気は変わっていないが、どこか憂いを帯びた表情をしていた。
「健太郎、よく来てくれた」瀬川が立ち上がり、私の手を握った。「みんな揃ったところで、まずは夕食にしよう」
第三章 最後の晩餐
食堂は豪華なシャンデリアに照らされ、長いテーブルには山海の珍味が並べられていた。
「久しぶりだね、健太郎」麻衣が微笑みかけてきた。「あなた、今は何をしているの?」
「フリーの編集者だよ。細々とやってる」
「そうなんだ。私も苦労してるのよ。最近、良い役がなかなか回ってこなくて」
山口が料理を頬張りながら口を挟んだ。「贅沢な悩みだな。俺なんて、毎日美味いもの食ってるけど、健康診断で引っかかりまくりだぜ」
北川が冷たく言った。「自業自得だろう。瀬川、それで今日は何の用だ?単なる同窓会とは思えないが」
瀬川はワイングラスを傾けながら、ゆっくりと口を開いた。
「実は、皆に謝らなければならないことがある」
一同の視線が彼に集中した。
「覚えているかい?大学四年の時、サークルの合宿で起きたあの事件を」
その言葉に、場の空気が凍りついた。
あの事件。十年前の夏、私たちは山中の別荘で合宿をしていた。そこで、サークルのメンバーだった藤原直樹が崖から転落して死亡したのだ。警察は事故として処理したが、真相は闇の中だった。
「あれは事故だったんだろう?」麻衣が不安そうに言った。
「いや、違う」瀬川は首を振った。「あれは事故ではなかった。そして、その真相を知っているのは、この中の誰かだ」
「何を言っている!」北川が立ち上がった。「証拠もないのに、そんなことを言うな!」
「証拠なら、ある」瀬川は静かに言った。「私は十年かけて調べた。そして、真実に辿り着いた」
「じゃあ、教えてくれよ」山口が緊張した面持ちで尋ねた。「誰がやったんだ?」
瀬川は一同を見回した。そして、口を開こうとした瞬間、館全体を揺るがすような轟音が響いた。
停電だった。
第四章 暗闇の中で
応接室に戻った私たちは、ろうそくの明かりの中で状況を確認した。執事の田中が言うには、山の天候が荒れて電線が切れたらしい。復旧には時間がかかるという。
「携帯も圏外だ」北川がスマートフォンを見ながら言った。「完全に孤立したな」
「まるでミステリー小説みたいだわ」麻衣が不安そうに呟いた。
瀬川は窓の外を見つめていた。「今夜は誰も外に出られない。そして、明日の朝、真実を明らかにする」
「待ってくれ」私は瀬川に近づいた。「さっき、誰かが藤原を殺したと言ったな。それは本当なのか?」
瀬川は振り返り、悲しげに微笑んだ。「ああ、本当だ。そして、犯人はこの中にいる。明日、すべてを話そう」
その夜、私は与えられた客室で眠れずにいた。窓の外では激しい雨が降り続け、時折雷鳴が轟いていた。
午前二時を過ぎた頃、廊下から悲鳴が聞こえた。
飛び起きて部屋を出ると、麻衣が青ざめた顔で立っていた。
「瀬川さんが……瀬川さんが!」
彼女が指差す先、瀬川の部屋のドアが開いていた。中に入ると、瀬川が書斎の椅子に座ったまま、首を垂れていた。
彼の背中には、鋭利なナイフが深々と突き刺さっていた。
第五章 密室の謎
私たちは書斎に集まった。田中執事が警察に連絡を試みたが、電話線も切れており、連絡は取れなかった。
「これは殺人だ」北川が冷静に言った。「警察が来るまで、現場を保存しなければならない」
「でも、どうやって犯人が入ったんだ?」山口が尋ねた。「ドアは内側から鍵がかかっていたんだろう?」
確かに、麻衣の証言では、ドアは施錠されていて、彼女の悲鳴を聞いた田中が合鍵で開けたという。窓も内側から鍵がかかっており、開けた形跡はなかった。
完全な密室だった。
「自殺の可能性は?」私が聞いた。
北川は首を振った。「背中にナイフが刺さっている。自分で刺すのは不可能だ」
「じゃあ、どうやって……」麻衣が震える声で言った。
私は部屋を詳しく調べた。書斎には大きな書棚があり、古い本がぎっしりと詰まっていた。暖炉もあったが、今は使われていないようだった。
机の上には、瀬川が書いていたらしいメモがあった。そこには、こう記されていた。
「真実は隠せない。罪は必ず明らかになる。藤原、許してくれ」
「これは何だ?」山口がメモを手に取った。
「遺書……いや、違う」北川が言った。「これは、何かを告発しようとしていたメモだ」
その時、私は机の引き出しに一冊のファイルがあるのに気づいた。開いてみると、そこには十年前の事件についての詳細な調査記録があった。
写真、証言、タイムテーブル。瀬川は執念深く真相を追っていたのだ。
そして、ファイルの最後のページには、こう書かれていた。
「犯人は──」
その後の文字は、インクが乾く前に誰かが濡れた手で触れたのか、滲んで読めなくなっていた。
第六章 それぞれのアリバイ
翌朝、雨は止んだが、霧はさらに濃くなっていた。私たちは応接室に集まり、昨夜の行動を確認することにした。
「まず、誰がいつ寝たか確認しよう」北川が言った。
麻衣が答えた。「私は十一時頃に部屋に戻ったわ。それから、ずっと部屋にいた。悲鳴を上げたのは、トイレに行こうとして廊下に出た時よ」
山口が続けた。「俺は十二時過ぎまで、一階の図書室で本を読んでいた。それから部屋に戻って寝た。悲鳴で目が覚めた」
北川は腕を組んで言った。「私は十一時半に部屋に入り、一時頃まで仕事のメールを書いていた。その後寝て、悲鳴で起きた」
「田中さんは?」私が尋ねた。
執事は丁寧に答えた。「私は使用人部屋におりました。十時には就寝し、麻衣様の悲鳴で目を覚ましました」
「健太郎は?」麻衣が私を見た。
「十一時には部屋にいた。ただ、眠れなくてずっと起きていた。悲鳴を聞いて、すぐに飛び出した」
北川が鋭い視線を向けた。「つまり、誰にもアリバイがないということだ。犯行時刻は午前二時前後。その時間、全員が単独で部屋にいたと主張している」
「でも、密室なんだぞ」山口が言った。「どうやって犯人は入って、出たんだ?」
私は書斎の構造を思い出していた。何か見落としているものがあるはずだ。
そして、ふと気づいた。暖炉だ。
第七章 暖炉の秘密
「暖炉を調べてみよう」私は提案した。
一同は再び書斎に戻った。私は暖炉の中を覗き込んだ。煤で黒くなった内部には、わずかに新しい擦過痕があった。
「この暖炉、どこかに繋がっているんじゃないか?」
北川が壁を叩いてみた。「確かに、空洞の音がする」
田中執事が言った。「実は、この館には隠し通路があるという噂を聞いたことがあります。ですが、旦那様からは何も聞いておりません」
「隠し通路……」麻衣が呟いた。
私たちは暖炉の内部を詳しく調べた。すると、奥の煉瓦の一つが動くことに気づいた。それを押すと、暖炉の奥の壁が回転し、狭い通路が現れた。
「やはりあったのか」北川が言った。
通路を進むと、階下の図書室の裏に繋がっていた。つまり、図書室から隠し通路を通って書斎に入ることができたのだ。
「これで密室のトリックは解けた」私が言った。「犯人は隠し通路を使って書斎に侵入し、瀬川を殺害した後、同じ道を通って逃げたんだ」
「じゃあ、犯人は図書室にいた人物……」麻衣が山口を見た。
山口は慌てて手を振った。「待ってくれ!俺は図書室にいたけど、そんな通路があるなんて知らなかった!」
「本当か?」北川が疑わしげに言った。
「本当だ!俺は本を読んでいただけだ!」
その時、私はあることに気づいた。ファイルの最後のページ。インクが滲んでいた理由。
「待ってくれ。犯人が誰かを決めつける前に、確認しなければならないことがある」
第八章 滲んだ文字
私は再び書斎に戻り、ファイルを手に取った。
「このインクの滲み方を見てくれ。これは単に濡れた手で触れただけじゃない。意図的に水をかけて、文字を消そうとした痕跡だ」
北川が頷いた。「つまり、犯人はファイルを見て、自分の名前が書かれていることを知り、それを消した」
「そうだ。だが、瀬川は賢い男だった。おそらく、他にも証拠を残しているはずだ」
私は部屋を再度調べ始めた。書棚、引き出し、あらゆる場所を探した。
そして、暖炉の脇にある小さな木箱を見つけた。開けてみると、中には古いカセットテープが入っていた。ラベルには「真実」と書かれていた。
「これを聞いてみよう」
幸い、書斎には古いカセットプレーヤーがあった。電池で動くタイプだったので、停電でも使えた。
テープを再生すると、瀬川の声が流れてきた。
『これを聞いている皆へ。もし私が死んだなら、それは真実を明かそうとしたからだ。十年前、藤原直樹は事故で死んだのではない。彼は殺されたんだ。そして、その犯人は──』
そこで、雑音が入り、しばらく何も聞こえなくなった。だが、やがて声が戻ってきた。
『──動機は嫉妬だった。藤原は才能があり、将来を嘱望されていた。だが、その才能を妬む者がいた。その人物は、藤原を崖に呼び出し、口論の末に突き落としたんだ。そして、それを目撃した人物がいる』
一同は息を呑んだ。
『目撃者は恐れて黙っていたが、私は証拠を見つけた。その証拠は、この館のどこかに隠してある。そして、犯人の名は──麻衣、君だ』
麻衣の顔が蒼白になった。
第九章 女優の告白
「違う!私じゃない!」麻衣が叫んだ。
だが、テープは続いた。
『麻衣、君は藤原を愛していたが、彼は君の気持ちに応えなかった。それどころか、他の女性に心を奪われていた。君は嫉妬に狂い、彼を殺してしまったんだ』
「嘘よ!そんなこと……」麻衣は泣き崩れた。
私は冷静に言った。「待ってくれ。これだけでは証拠にならない。瀬川が言っていた証拠を見つけなければ」
私たちは館中を探した。そして、図書室の本棚の裏に隠された小さな金庫を見つけた。
鍵はなかったが、北川の法律知識で開け方を見つけ、開錠した。
中には、一本のビデオテープが入っていた。
「これを見よう」
停電しているため、私たちは発電機を動かしてテレビとビデオデッキを使った。
画面に映ったのは、十年前の合宿の映像だった。誰かが隠し撮りしたものらしい。
映像には、夜の崖で口論する藤原と麻衣の姿があった。
「なぜ私を愛してくれないの!」麻衣が叫んでいた。
「悪いけど、君のことはそういう風に見られない」藤原が冷たく言った。
「じゃあ、誰なの?あの女なの?」
「それは言えない」
麻衣は激昂し、藤原を押した。だが、藤原はバランスを崩し、崖から転落した。
麻衣は呆然と立ち尽くし、やがて走り去った。
映像はそこで終わった。
第十章 真実と虚構
「これで証拠は揃った」北川が言った。「麻衣、君が藤原を殺したんだな」
だが、私は首を振った。
「いや、違う。これは演技だ」
「何?」一同が私を見た。
「よく見てくれ。この映像、照明がおかしい。夜の崖なのに、まるでスタジオで撮影したかのように明るい。そして、藤原の転落シーンも不自然だ。本当に崖から落ちたのなら、もっと悲鳴や動きがあるはずだ」
北川が映像を巻き戻して確認した。「確かに……これは再現映像か?」
「そうだ。瀬川は私たちを試したんだ。真実を見抜けるかどうか」
「じゃあ、本当の犯人は?」山口が尋ねた。
私は瀬川の書斎に戻り、もう一度ファイルを見た。滲んだ文字。私は特殊なライトを当ててみた。すると、薄く文字が浮かび上がった。
「犯人は──田中」
一同が執事を見た。
田中は静かに微笑んだ。「よくお気づきになりましたね」
第十一章 執事の罪
「なぜだ?」私が尋ねた。
田中は深く息をついた。「藤原直樹は、私の息子だったんです」
一同は驚愕した。
「藤原は私の隠し子でした。若い頃の過ちで生まれた子を、私は認知せず、母子家庭で育てさせました。だが、藤原は優秀で、奨学金で大学に入りました」
「それと今回の事件と、何の関係がある?」北川が尋ねた。
「瀬川さんは、藤原の死の真相を調べるうちに、私が父親だったことを知りました。そして、私に問い詰めてきたんです。なぜ息子を助けなかったのか、と」
田中の目には涙が浮かんでいた。
「藤原は確かに事故で死にました。ですが、私は彼を助けられたかもしれない。あの夜、崖の近くにいたんです。息子を遠くから見守っていました。だが、彼が崖から足を滑らせた時、私は恐れて助けに行けなかった。自分が父親だとバレることを恐れて」
「それを瀬川さんに責められたのか」私が言った。
「ええ。瀬川さんは言いました。『あなたの臆病が、藤原を殺したのだ』と。私はその言葉に耐えられず……昨夜、隠し通路を通って書斎に入り、瀬川さんを殺害しました」
「だが、なぜ今頃になって?」山口が尋ねた。
「瀬川さんが真実を公表すると言ったからです。私の名誉も、この館での職も、すべて失うことになる。私は臆病でした。十年前も、そして今も」
第十二章 霧の向こう
翌日、霧が晴れ、警察が到着した。田中は素直に罪を認め、連行されていった。
私たちは館を後にする準備をしていた。
「瀬川は、なぜこんな残酷な試練を用意したんだろう」麻衣が呟いた。
私は答えた。「彼は真実を明らかにしたかった。だが、同時に私たちを試したかったんだと思う。人は過去の罪に、どう向き合うべきか」
北川が言った。「結局、彼自身が犠牲になった。それは計算外だったんだろうな」
山口が頷いた。「悲しい結末だ」
私たちは霧の館を後にした。振り返ると、館は再び霧に包まれ、まるで幻のように消えていった。
十年前の事件の真相は、こうして明らかになった。だが、瀬川恭介という男は、真実を追い求めるあまり、自らの命を失った。
真実は人を救うこともあれば、破滅させることもある。
私はそう思いながら、山を降りていった。
車窓から見える景色は、相変わらず霧に覆われていた。だが、その向こうには、必ず晴れた空があるはずだった。
-完-



コメント