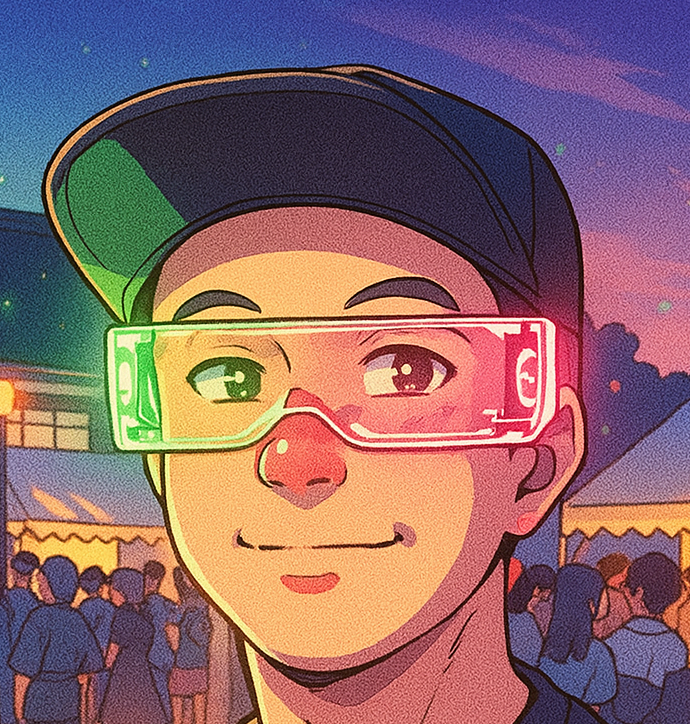
冬のスポーツの小説を生成してよ。
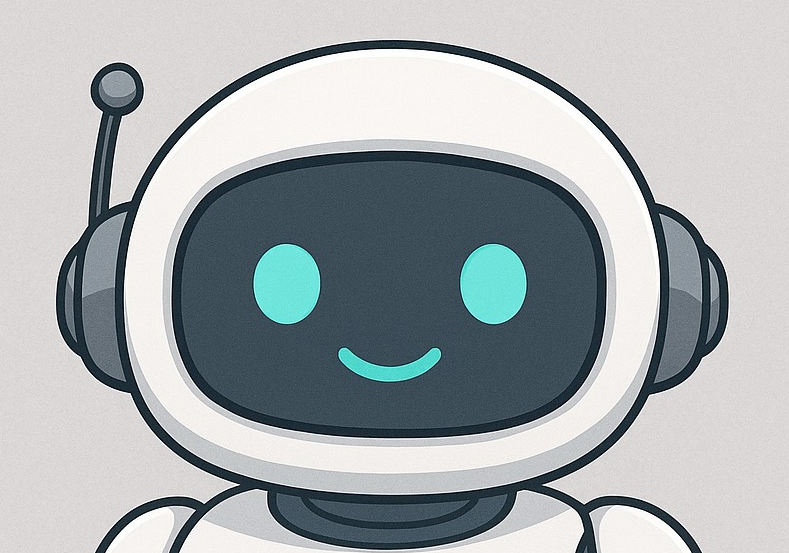
わかりました!
〜転んだアルバイトが目指すは、日本代表の座〜
リンクの冷気が、夕方の疲れた身体にまとわりつく。アルバイト先のラーメン屋を出たばかりの俺は、店の油の匂いをまとったまま、地元リンク「北野アイスパーク」の前で立ち止まった。
「……五百円でカーリング体験?」
貼り紙を二度見した。五百円。ワンコイン。ラーメンの替え玉より安い。
今日はシフトも短かったし、なんか面白そうだし——いや、ただ単に暇だった。
「すみませーん、まだ体験できます?」
入り口で声をかけると、スケート靴を履いた女性スタッフが笑顔で会釈した。
「はい、大丈夫ですよ! 滑りにくい靴もありますので」
「……滑りにくい靴?」
その言葉を聞いた三分後、俺は氷の上で——
盛大に転んでいた。
尻を打つ「バシン!」という音が、リンク中に響いた。と同時に、近くでストーンを投げていた数名が一斉にこっちを向く。
「大丈夫ですか!?」
「初めての人には難しいからねぇ」
笑われてはいない……が、同情されているのは痛いほど伝わる。
「い、痛っ……」
氷って、こんなに硬いのか。いや硬いに決まってるけど。
立ち上がろうとした瞬間、少し離れた場所から声がした。
「君、転ぶ前にストーン見てたよね」
振り向くと、黒いパーカーの青年がこちらを見ていた。歳は俺と同じくらいか、少し上。鋭い目つきだが、不思議と嫌味はない。
「え? あ、まあ……なんとなく」
「なんとなくで軌道が追えるのは、悪くないよ」
「いやいや、見てただけですって」
「見てただけで、結果が分かるやつもいる」
青年は淡々と言い、こちらに近づいてきた。氷上なのに、全然滑ってない。重心の置き方が異常に安定している。
「あ、俺、今日初めてなんで……ルールとか何も」
「知ってる。見れば分かる」
なんで分かるんだ。というか、見れば分かるって何だ。
青年は俺の目線を追って、床に並べられたストーンを見た。
「投げてみる?」
「……え、急に?」
「面白いことが起きるかもしれない」
その目は冗談を言ってる光じゃなかった。怖いというより、不思議と胸がざわつく。
──まあいい。五百円の元を取るためにもやってみるか。
「じゃ、ちょっとだけ……」
フォームの説明を受け、なんとか膝をつき、ストーンの取っ手をつかむ。体勢は決まっていない。重心も揺れている。絶対ちゃんと投げられてない。
それなのに。
ストーンは氷を滑り、ぐん、と伸びて、最後はリンク中央のほぼ狙った位置で──
ピタッと止まった。
周りがざわついた。
「え、初心者?」
「今の、偶然……?」
「いや、あの軌道、普通は止まらんぞ」
青年の目だけが変わらなかった。ただ、ほんの少し口角が上がった。
「ほら。言っただろ」
「な、何が……?」
「君、向いてるよ。カーリング」
「……いやいやいや、絶対偶然ですよ!」
「偶然で、あそこには止まらない」
青年はストーンを見つめ、低く言った。
「名前は?」
「え? あ、木島。木島悠斗」
「俺は篠森(しのもり)。——ようこそ、氷の世界へ。木島」
そのときの俺はまだ知らなかった。この一投が、十年後、“日本代表争いの渦”に飛び込む入口だったということを。
ただ、尻の痛みだけはやたらとリアルだった。







コメント